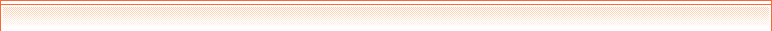「そもそも“浮世絵”ってなんだ?」と思ったのでちらっと調べたのを。
・浮世絵はもともと肉筆画
四条派、狩野派などの幕府がバックに付いていない町絵師が描いた
・浮世絵=「浮世人物」を描く絵のこと
・初期浮世絵
当時の一般庶民が最も興味を引く自分たちの人間社会をテーマにした
歌舞伎(役者)&遊郭(美人画)
浮世絵の創始者の菱川師宣は、武家中心を描いた
庶民により、庶民大衆の為に描かれた絵画
(土佐、狩野派の官学的画法から区別されていた町絵師が自前のスタイルを確立)
・太夫=当時最高の教養&遊芸に秀でていた
庶民の理想の女性
・元禄頃になると、肉筆で風俗を描いてきた浮世絵に版画が採用
=複数芸術として庶民の施行に合った題材が積極的に描きだされる
(庶民にとって、肉筆画より浮世絵の方が廉価だった為、浮世絵の方が普及)
題材はやっぱり歌舞伎役者と、遊郭の遊女
(引用:「浮世絵の歴史 【美人絵・役者の世界】」
・・・・ここから個人的に解釈すると、浮世絵は当時の理想の人物像を描いたものか、とか。
(人気のある人物を描いていた)
今で言う、写真とかそういう類?
歌舞伎が今でいうテレビみたいな役割だったらしいからそう考えてもいいかも。
まだまだ何かあったら書いていきまーす。

PR