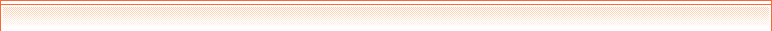一通りにサイズが解ったので。
こんなに種類があったんだーと妙に感心しました。
これで制作のサイズの参考になるぞー!!・・・いやなったらいいな。
しかしこんなに種類があったとは。びっくり。
・・・・・・・・・・・・
サイズ(浮世絵版画の判型) 詳細「浮世絵の観賞基礎知識」 著:藤沢紫
・美濃紙(約33×46cm)から裁断された判型
(1764年以前の初期浮世絵に多く使われた)
1:大々判(約30~33×55~65cm)
(大判に別紙を継いだもの)
2:大判(約33×46cm)
3:細版(約33×15~16cm)
・大広奉書-おおひろぼうしょ-(約44×58cm)から裁断した判型
(1764~72に多く使われた)
1:中判(約29×22cm) 約1/4
鈴木春信がよく使っていたので「春信判」と称される
・大奉書(約39×53cm)から裁断された判型
(錦絵に最も良く使われた)
1:大倍判(約39×53cm)
2:大判(約39~26×27cm) 1/2
「大錦」とも称される代償的な判型
3:中判(約26×19.5cm) 1/4
4:四つ切判(約19.5×13cm) 1/8
・小奉書‐こぼうしょ‐(約33×47cm)から裁断された判型
(大奉書についで良く使われていた)
1:間倍書‐あいばいしょ‐(約33×47cm)
2:間倍(約33×23cm)間倍書の1/2
「間錦」とも称され、続絵によく使われていた。
3:小判(約23×16.5cm)間倍書の1/4
4:細判(約33×15cm)間倍書の1/3
役者絵によく使われていた。
・丈長奉書‐たけながぼうしょ‐(約53×72cm)から裁断された判型
(1736年頃から浮絵や柱絵などに使われた)
1:丈長奉書全判(約53×72cm)
2:幅広柱絵(約69~75×17~26cm) 1/3~1/2
「大々判」「大長判」「掛物絵」とも称される
3:柱絵(約69~70×12~13cm) 1/4
本日のBGM:DRAGON RISES By澤野弘之 「医龍2」サントラ

PR